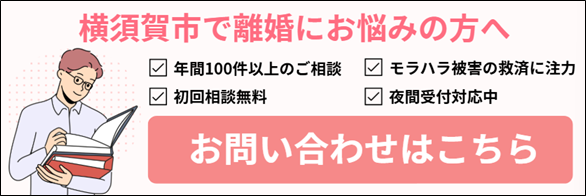面会交流について
離婚後に親権がない親と子どもが会う機会である面会交流ですが、昨今裁判所の対応に変化があり、気を付けておきたいことが増えつつあります。
そんな面会交流についてここでは説明していきます。
1 面会交流とは
面会交流とは、監護権のない親と子どもが面会することをいいます。
家庭裁判所は、一緒に暮らさない親との面会交流は、子どもの健全な成長に不可欠と考えており、余程の事情がない限り、月1回程度実施されるのが殆どとなっています。
離れて暮らす親の権利と考えられがちですが、実際は子どもの権利でもあるため、会いたい親の意思も大切なのですが、優先されるのは子の福祉、すなわち、子どもにとって有益かどうかになります。
面会交流をとおして離れて暮らす親からも愛されていることを実感し、安心感や自信を得ることはとても大切であり、そのことが子どもの健やかな成長に繋がると裁判所は考えているのです。
2 面会交流を実施する期間
面会交流を行うのは、基本的に子どもが成人するまでとされています。
ただ、中学生くらいになると本人の意思が重要視されるので、
「会いたくない」
と言われてしまったら、そこで実施されなくなることもあります。
逆に、子どもがもっと会いたいといえば、一人でも会いに行ける距離であれば、自由に行き来する場合もあります。
3 面会交流について取り決める内容
面会交流について以下のような内容で決めることが多いです。
① 面会交流の頻度 月に1回が圧倒的です
② 面会交流の場所 細部まで詰めず、実施日が決まった後に決めることが多いです
③ 面会交流の時間 細部については都度実施されること決まった後に決めることが多いです。
④ 子どもの引き渡し方法 ここまで決めるのは稀ですが親権者が非協力的の場合決めることがあり得ます。
⑤ 学校行事への参加の可否 運動会など遠くから見守れる行事のみとされることが多いです。
⑥ 面会交流に関する連絡方法 接触が少なくなる方法が推奨され、LINEは余計な事まで言うことが多く、あまりお勧めできません。
殆どの事案では、
「月1回程度認める。具体的な日時、場所、方法は子の福祉に配慮して双方協議して決める」
という規定になることが多いです。
4 面会交流を取り決める方法
面会交流は、夫婦間の協議、または家庭裁判所の手続である調停・審判のなかで取り決めます。
① 夫婦間の協議
まずは、夫婦間で面会交流の可否やその条件について話し合います。
話し合いの場合には、子どもの福祉・利益を最優先に考えることを前提として、柔軟に条件を取り決めることが可能です。
② 調停・審判
協議でまとまらない場合、面会交流調停を申し立てることになります。
細かい点の調整だけなら話し合いで決まりますが、双方の乖離が大きい場合、家庭裁判所の調査官が子どもの意思、両親の移行や従前の監護状況、家庭や学校での生活状況を調査して、面会交流をどのように実施するのか決定します。
面会交流が具体化できない事情があるときは、裁判所の部屋を用いての試行的面会交流を実施する場合があります。
親権のない親と子の交流をマジックミラー越しに親権のある親や裁判所調査官が見ながらの実施となります。
裁判所での実施のため、安心して行うことが出来ます。
その様子を見て調査官は、どの程度の実施が可能か判断していきます。
調査官調査後は、調査結果を前提にした調停での話し合いで大半は解決しますが、それでも溝が埋まらない場合審判に移行して、裁判官が面会交流の内容について判断をします。
5 交流が認められないケース
調停・審判において、裁判官が面会交流の実施が子どもの福祉に合致しないと判断した場合、面会交流は認められません。
・子どもが面会交流を明確に拒否しているケース
・子どもの生活に悪影響を及ぼすおそれがあるケース
・子どもを連れ去られる危険性があるケース
・非監護親に違法行為があるケース
・別居・離婚の原因が暴力・DVであるケース
などでは、直接会う面会交流の実施を見送り、写真や動画の送付といった間接的な交流の実施になることがあります。
これは、面会交流で最重要視されるのは、あくまでも子の福祉であり、子どもにとって負担や悪影響になる場合には、面会交流を実施すべきではないという家庭裁判所の考えに基づきます。
6 面会交流を拒否するリスク
面会交流は、子どもの福祉・利益に寄与する限り、監護権のある親の都合で拒否することはできません。
ただ、実際は、面会交流させたくないという方が結構いらっしゃいます。
しかし、正当な理由なく面会交流の実施を拒否すると、以下のような法的手続をとられるおそれがあります。
① 裁判所から履行勧告を受ける
履行勧告とは、家庭裁判所から調停や審判で取決めた内容を守りなさいと指導を受けることです。
履行勧告に強制力はありませんが、裁判所から電話や書面で連絡がくると、プレッシャーを感じることになるでしょう。
② 間接強制を申し立てられる
間接強制とは、調停や審判で取決めた約束に応じるまでの間、監護親に金銭の支払義務を課すことで面会交流を実施するよう促す手続です。
たとえば、裁判所から「面会交流に応じない場合には1回につき○万円を支払うように」といった命令を受けるおそれがあります。
間接強制金の金額は、約束の不履行1回につき3万円~10万円程度であることが多いようです。ただし、監護親の収入が特に高いケースでは、10万円を超えることもあります。
弁護士の印象としては、「この状況でこの金額か」と思うような高額な金額に設定されることが多いです。
それくらい面会交流を実施しないことは重大な違反ととらえているようです。
約束したのに会わせないのではなく、面会交流の取り決めをする際に合わせたくない理由を主張する他ありません。
③ 慰謝料を請求されるおそれがある
正当な理由なく面会交流を拒否すると、非監護親から「子どもに会えず精神的苦痛を被った」として慰謝料を請求されるおそれがあります。
④ 親権者変更を申し立てられる
正当な理由なく面会交流を拒否し続けると、「子どもの健全な成長に悪影響を及ぼす可能性がある」として親権者変更を申し立てられるおそれがあります。
7 面会交流を行うときの注意点
面会交流を行う際には、以下の点に注意しましょう。
① お互いに約束やルールを守る
無用なトラブルを防ぐためにも、面会交流の日時や場所、引き渡し方法など、取り決めた内容はお互いに守るようにしましょう。
② 監護親・非監護親の双方が子どもやお互いに配慮をする
面会交流に対してあからさまに不満そうな態度をとったり、非監護親の悪口を言ったりすることは避けるべきでしょう。
③ 夫婦関係と父母関係を切り離して考える
面会交流は、あくまで子どもの福祉や利益のためのものです。夫婦関係と父母としての関係は切り離して考え、子どものためにお互いを信頼することも重要になります。
④ 子どもの負担を考慮する
面会交流を行う際、子どもの都合を無視した日程を設定してしまうと、大きな負担になってしまいます。
8 第三者機関を利用する方法
父母間で直接接触することが難しい場合や、子どもが連れ去られないか不安がある場合には、第三者機関を利用して面会交流を行う方法もあります。
面会交流の第三者機関とは、自治体・民間団体による円滑な面会交流の実施を支援する機関です。利用には費用がかかりますが、面会交流の調整や、子どもの引き渡し、立ち合いなどを代わりに行ってくれます。
以上、面会交流について説明してきました。
親の子への想いは非常に強いものがあり、双方中々譲らないため、ハレーションが起きることが多々あります。
私の場合は、監護権者には面会交流をすることの重要性を納得してもらう、非監護権者には面会交流をスムーズに実施するために寛容性を持ってもらうことを大切にしています。
弁護士の中には、敵意剝き出しにして相手を攻撃することも多々あり、かえって事件を紛争化させることも増えていますが、大きな疑問を感じています。
面会交流はご自身にとってはもちろん、お子様にとって非常に重要な問題ですので、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
数多くの面会交流事件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

島・鈴木法律事務所
代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
当サイトでは、離婚問題にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。|弁護士紹介はこちらをクリック>>
- 2025.12.23 令和6年の民法等の改正による面会交流はどうように変更されるのか?
- 2025.12.23 財産分与をせずに一定の解決金のみで早期に調停離婚した事案
- 2025.11.27 不貞した財産のない相手から慰謝料を獲得して調停離婚した事案